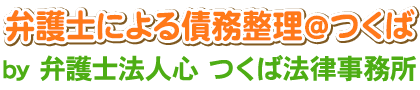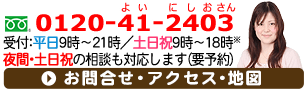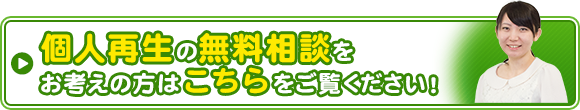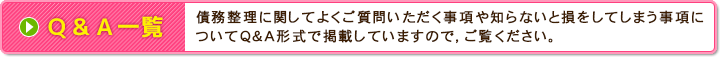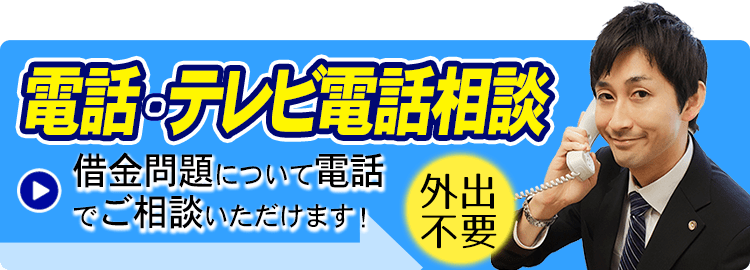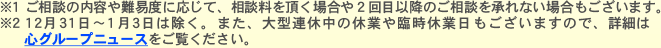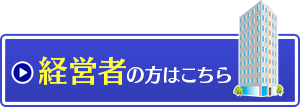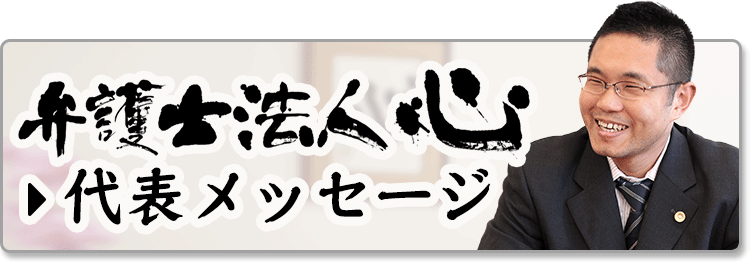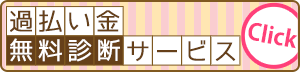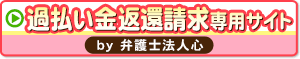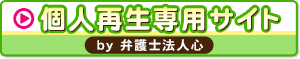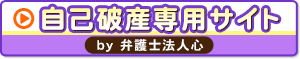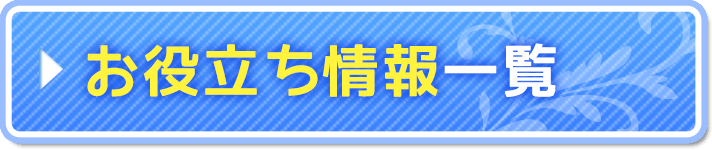「個人再生」に関するお役立ち情報
金利が上昇して住宅ローン返済が困難になった場合の個人再生
1 住宅ローン以外の債務を減額して自宅を残せる可能性があります
変動金利型の住宅ローンを組んでいる場合、金利が上昇すると月々の住宅ローン支払額も高くなります。
支払額の上昇幅には制限があるものの、毎月の支払額が増えると生活費等へ影響が生じることがあります。
特に住宅ローン以外の借金等の返済も行っている場合は、住宅ローンの支払いによって他の借金の返済に支障が生じてしまうこともあるかもしれません。
このような状況に陥ることを解決する方法のひとつとして、個人再生が挙げられます。
個人再生を行い、その申立て内容が認められますと、借金が大幅に減額されます。
また、一定の条件を満たせば、住宅ローンのみを減額の対象から外し支払いを継続することが認められますので、自宅に設定された抵当権が実行されることを回避し、そのまま自宅に住み続けることができます。
以下、個人再生と住宅ローンの関係、および自宅がある場合の返済額への影響等について説明します。
2 個人再生と住宅ローンの関係
個人再生は裁判所を介して行われる債務整理手続きであり、債務総額を大幅に減らせる可能性があります。
すべての債権者が対象となる手続きですので、住宅ローンの借入先も原則として対象に含まれます。
本来、住宅ローン会社を相手に債務整理をした場合には、抵当権が実行され、自宅は差し押さえられて競売にかけられてしまいます。
しかし、個人再生には、住宅ローンだけは従来どおり支払い、他の債務を減額することで、自宅に設定された抵当権の実行を回避できるという制度が設けられています。
この制度を、「住宅資金特別条項」といいます。
住宅資金特別条項の利用には一定の条件を満たす必要があります。
主な条件についてはこちらのページに記載しておりますのでご確認ください。
弁護士に個人再生を依頼し、住宅資金特別条項の利用を希望する場合、その旨を債権者に通知することで、抵当権の実行が保留されます。
裁判所に個人再生の申立てをする際には、住宅資金特別条項を利用する旨の申立てもします。
申立て後、裁判所による精査を経て再生計画案が認可されると、住宅ローン以外の債務が減額されます。
再生計画認可後は、減額後の債務と住宅ローンの支払いを行っていきます。
3 自宅がある場合の返済額への影響
自宅などの不動産を所有している場合、個人再生後の返済額が大きくなる可能性があります。
個人再生には、法律で決められている最低弁済額と、債務者の方に属している財産評価額の、いずれか高い方を返済しなければならないというルールがあります。
このルールを、「清算価値保障原則」といいます。
自宅の査定額と比べて住宅ローン残高が低い場合(いわゆるアンダーローン)、差額分が清算価値に算入されます。
不動産価格の高騰などによって、差額分が大きくなった場合、個人再生後の返済額も大きくなります。
個人再生でも解決ができない場合、自己破産を検討する必要があります。
所有している財産と個人再生の返済額 個人再生の履行テストとは