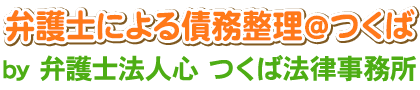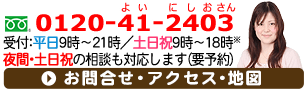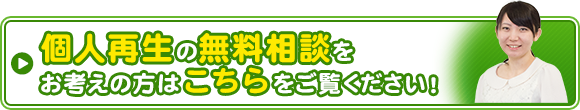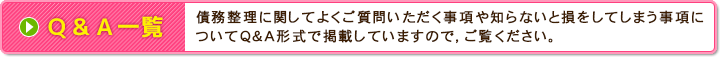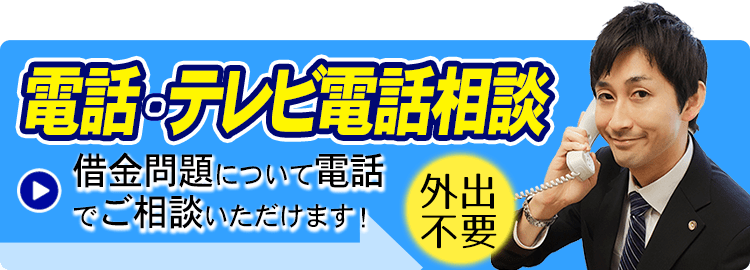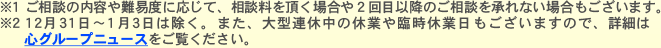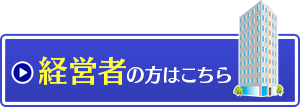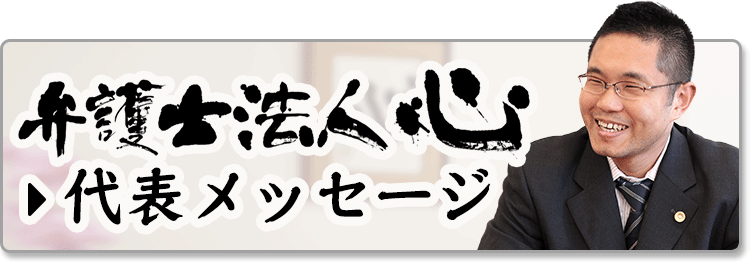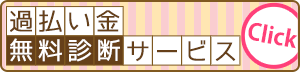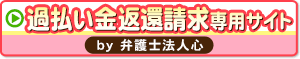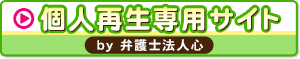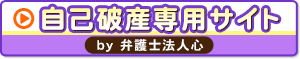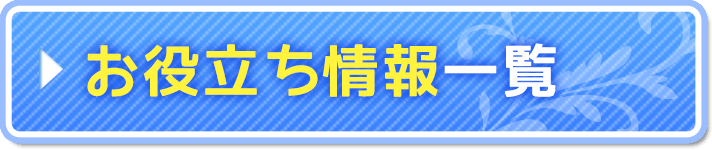「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生で家を残す方法
1 住宅資金特別条項が利用できれば家を残すことは可能
個人再生においては、一定の条件を満たすことで、住宅ローンの支払いを継続して自宅に設定された抵当権の実行を回避しつつ、その他の債務を減額できる制度が設けられています。
この制度は、専門的には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)と呼ばれます。
住宅資金特別条項を利用できれば、生活の拠点である自宅を守りつつ、生計を立て直すことが可能となります。
個人再生手続きの大きな特徴です。
2 債務整理と抵当権の実行との関係
住宅ローンを組む際には、通常であれば金融機関等が自宅不動産に抵当権を設定します。
債務者の方の返済を滞った場合や、債務整理を行った場合には、抵当権が実行され、自宅不動産の競売(実務上は任意売却のことも多いです)により債権が回収されます。
3 住宅資金特別条項の利用
個人再生はすべての債権者を対象とする債務整理の手続きですので、住宅ローン会社も対象となります。
弁護士に個人再生を依頼し、弁護士から住宅ローン会社へ受任通知が送付されると、本来的には抵当権が実行されます。
もっとも、住宅資金特別条項が利用できる見通しがある場合、受任通知にその旨を記載しておくことで、抵当権の実行は留保されます。
住宅資金特別条項を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主な要件は次のとおりです。
①対象の住宅が債務者本人または家族の居住用であること
②住宅ローンが住宅の購入やリフォームのための資金であること
③住宅に他の抵当権が設定されていないこと
住宅資金特別条項が利用できる場合、個人再生後も住宅ローンは従来とおりに支払い続けることになります。
住宅ローン以外の、消費者金融からの借入金やクレジットカードの立替金債務などは減額され、原則として3年間で分割返済をしていきます。
ただし、住宅ローンを滞納して代位弁済がなされている場合や、住宅ローン残高が少なく保有財産の評価額が高い場合には、住宅資金特別条項の利用ができない可能性もあります。
実際に制度を利用できるか否かについては、できるだけ早めに弁護士に確認しましょう。