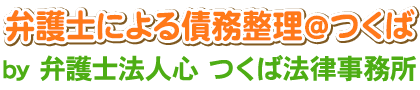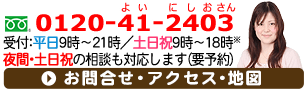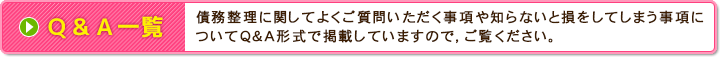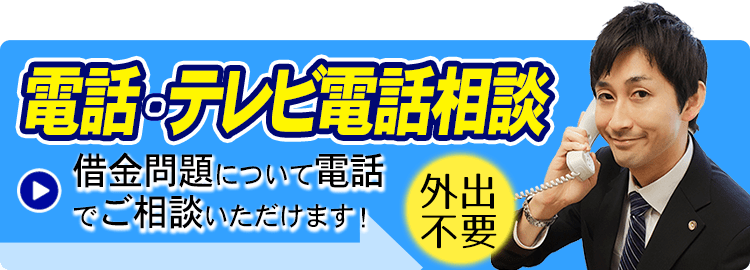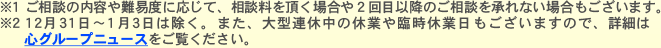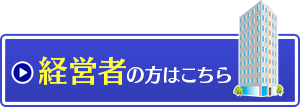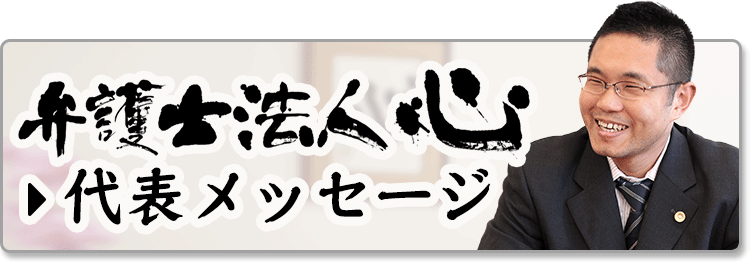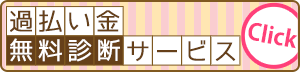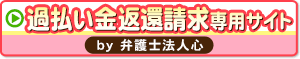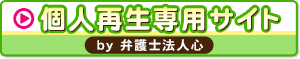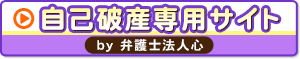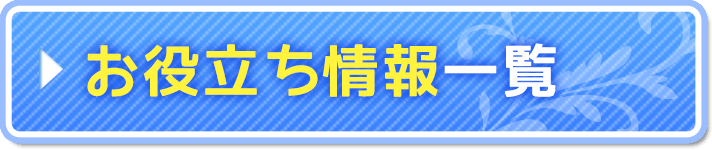「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理における和解とは何か
1 任意整理における和解とは返済条件を変更すること
任意整理では、お金を借りた側と貸した側が話し合って、返済総額や分割回数などの返済条件を変更することができます。
互いが納得する条件に変更できれば、和解が成立したと言えます。
返済条件の交渉の際は、債務者の方が毎月どれくらいの金額を返済に充てられるかや、貸金業者側がどれくらいまで譲歩してくれるかの傾向等を把握した上で進める必要があります。
また、貸金業者等から訴訟を提起されている場合といない場合とでも、交渉の仕方や和解の形式が異なることがあります。
任意整理を行う際は、依頼先の弁護士に現在の状況等をしっかりと伝え、どのような和解が見込めるか等を事前に確認されることをおすすめいたします。
2 任意整理の流れと和解
実際に任意整理を行う際の簡単な流れと和解について説明します。
⑴ 返済条件の検討
任意整理をすると、一般的には残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割して返済できるようになります。
債務額から算定した任意整理後の想定返済額よりも、債務者の方の返済可能額が上回っている場合、任意整理をすることができます。
まずは収入と支出を正確に把握し、返済可能額を算定します。
その金額と債務額を比較して、最低分割回数を決めていきます。
⑵ 訴訟を提起されていない場合の和解
最低分割回数の算定ができたら、最低分割回数以上の回数で分割返済をするという条件で和解したい旨を、貸金業者等に対して提案します。
交渉の結果、合意に至ることができたら、和解書を作成して任意整理は終了します。
その後、改めて和解書の内容に従って返済を行っていきます。
⑶ 訴訟を提起されている場合の和解
状況によっては、貸金業者等が訴訟を提起して、残債務等の返済を請求することがあります。
訴訟になったからといって、必ずしも判決まで至るというわけではありません。
裁判外で貸金業者等との話し合いを進め、当事者同士が合意できる返済条件に変更が可能なのであれば、その内容を裁判所に伝えることで、裁判上の和解(簡易裁判所においては、和解に代わる決定と呼ばれます)をすることができます。
訴訟への対応と裁判外での任意整理交渉を同時に進める必要があり、臨機応変な対応が求められますので、弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。
預金の差押えを受けた状態から任意整理できるか リボ払いでできた債務も任意整理はできるのか